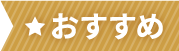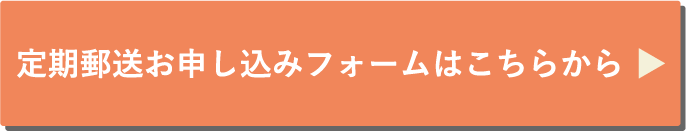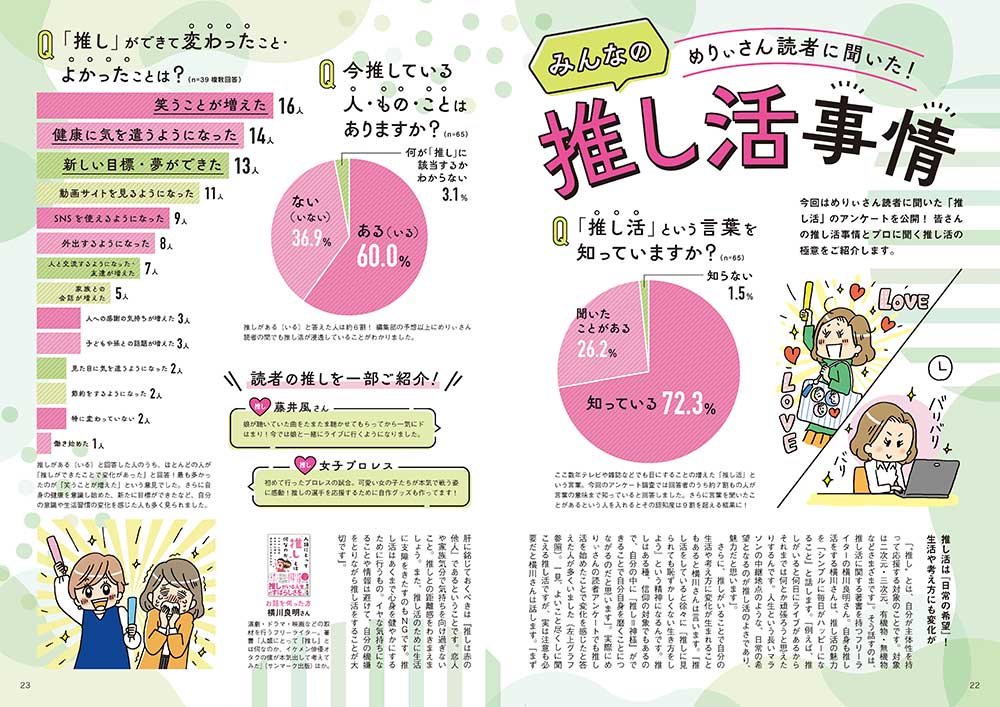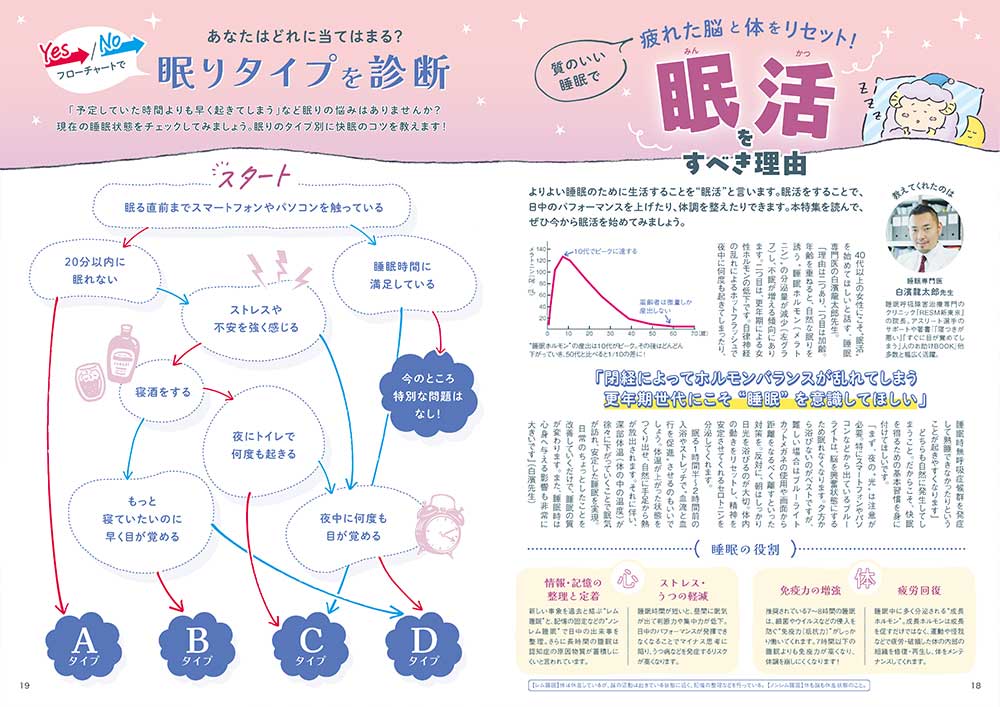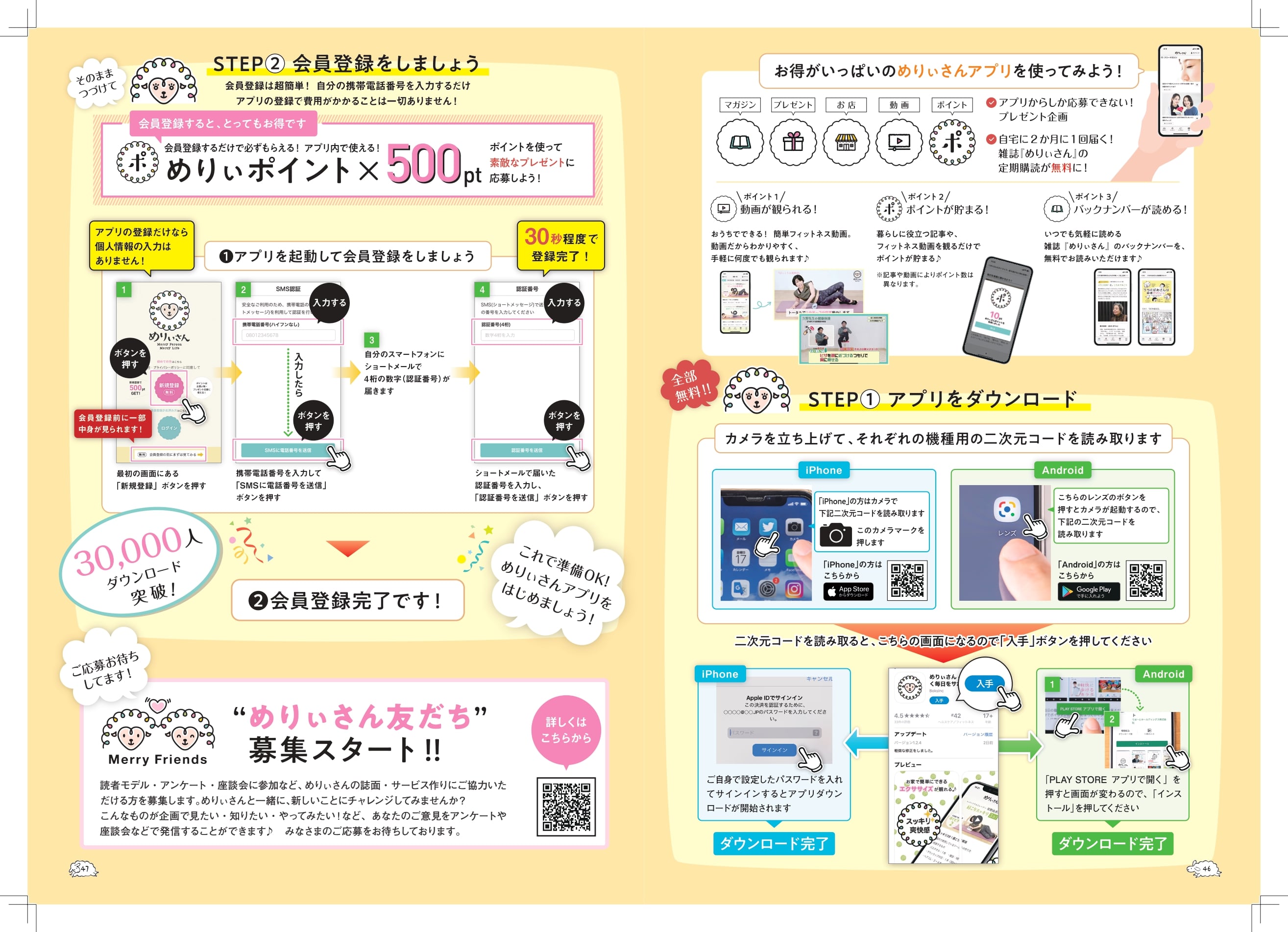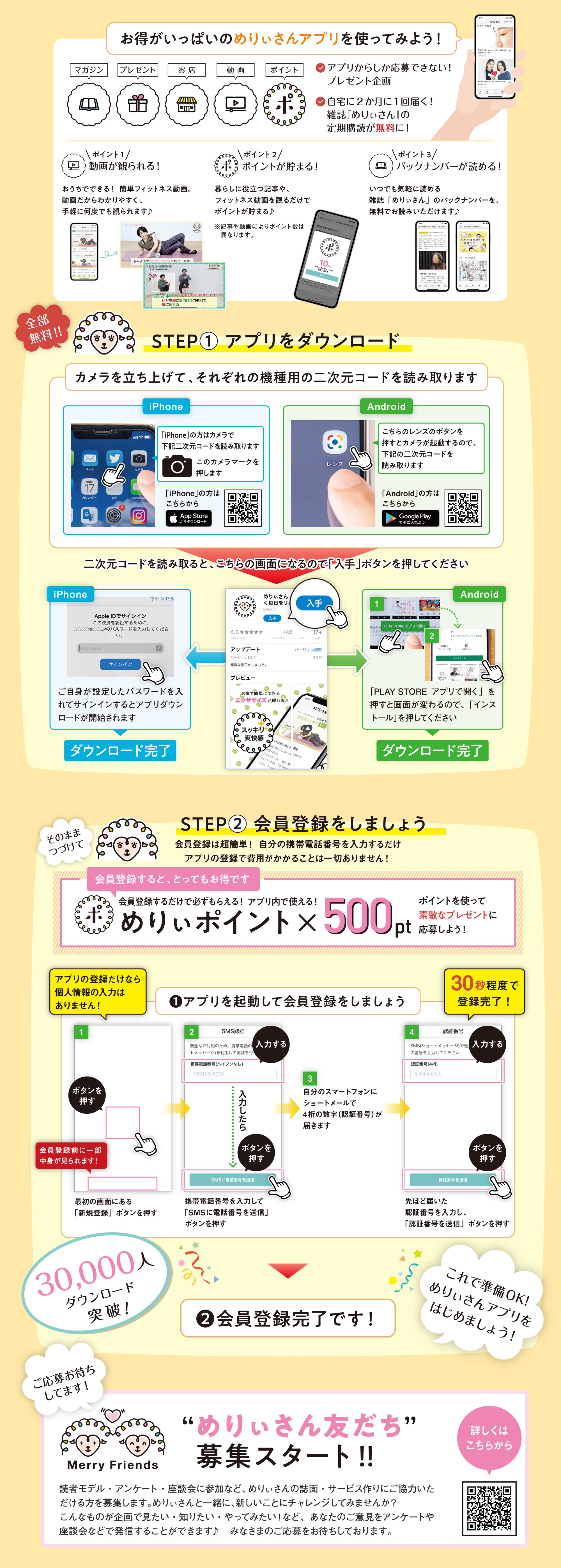スペシャルインタビュー 安藤和津さん

撮影/松本 健 ヘア&メイク/高瀬央子
スタイリング/松田綾子 取材・文/明滝 園
ワンピース¥19,800、ネックレス¥8,800(ともにDUEdeux 03-6228-2131)
サンダル¥20,900(HIMIKO https://www.himiko.jp/)
エッセイストであり、テレビのコメンテーターとしてもおなじみの安藤和津さん。
2018年にはお母さまの介護とご自身のうつの体験を綴ったエッセイを出版しました。
うつを乗り越え、今ご自身が大切にしていることや、日々の楽しみについて伺いました。
いつもと違う日々の中で家族と過ごせた幸せ
これまでの当たり前が当たり前ではない生活が続き、私もここ1年半で生活スタイルが大きく変わりました。
外出の機会が減って、生活雑貨などの必需品はもちろん、洋服や靴までほとんどのものをネット通販で購入するようになりました。
昨年、東京に緊急事態宣言が出たとき(2020年4月7日)、私はちょうど夫の新作映画の下見で、高知県に移住した長女の家を訪れていました。ほんの数日の予定でしたが、事務所から宣言が解除されるまで高知県に留まるようにと指示があり、それから結局2か月半ほど娘や孫と暮らしました。
制限のある生活でしたが、孫と過ごせたことは幸せでした。楽しい時間だけをつまみ食いするのではなく、一日中家族全員で家にいたからこそ、孫に料理を教えたり、一緒に掃除をしたり、音楽をかけて三世代でおうちディスコで踊ったりなんてこともできました。
友人の中には、「コロナ禍で孫と会えない」という人もいましたから、数か月間だけでも孫と充実した時間を過ごせたことはうれしかったし、貴重な体験だったと思います。変わってしまった日常の中にも、たくさんの幸せがあると感じられる日々でした。

日々の健康をつくるのは「質素な贅沢」
高知県に滞在していたとき、家の近くに山があるので山菜採りに行きました。
フキやゼンマイを摘んで、筋取りやあく抜きなどの下処理から調理までやってみて、ひと手間かけることの大切さに改めて感動したのを覚えています。昔の人々はみんなこうやって一つ一つの工程を経て、料理をつくっていたのですよね。手間をかけることで美味しさも倍増し、食の尊さを痛感しました。
そして、自然のエネルギー溢れる食は身体を元気にしてくれるのだなと実感。健康づくりって、結局は日々の食事の積み重ねが大きく影響すると思います。
無農薬の野菜はお塩もいらないくらい味が濃いから、そのままでも十分。お米やお味噌、野菜など、基本となる食材をどれだけきちんと選んで、味わって食べているかが大事で、豪華じゃなくていい。
自然のものを食べることが健康づくりのベースであり、私はそれを「質素な贅沢」と言っています。大切なもの、自分に本当に必要なものを選ぶ力を大切にしたいです。
介護中も介護後も続いたうつ。50代は真っ暗闇だった
40代後半から12年間、母の介護を経験しました。仕事に追われる私や夫をサポートしてくれ、一家の大黒柱のような存在だった母。
老人性うつ病、さらに認知症と診断された母でしたが、家族みんなで話し合い、在宅で介護をすることを決断しました。
でもそれが、母には手づくりの美味しいものを食べさせなきゃ、2時間おきにおむつを交換しなきゃ、ヘルパーさんにはあまり頼らず私が頑張らなきゃ……と、私自身にプレッシャーをかけることになってしまって。
どんどん自分を追い込んで、オーバーワークのパンク状態に。夜中に何度も私を呼ぶ母に起こされ、睡眠不足で毎日ふらふらでした。
自分の時間やエネルギーのほとんどが母の介護に費やされ、いつまでこのような生活が続くのかと思うと、目の前が真っ暗になったように感じました。
無理に笑っていた日々。うつを隠す必要はなかった
母が亡くなり、介護が終わったことで私自身はうつから抜けられると思っていました。
ところがうつは「燃え尽き症候群」とかたちを変え、今度は介護後うつになってしまったのです。
人前に出るときは「元気だった頃の私なら、こう振る舞うはず」と、自分を偽っていました。
「苦しい! 助けて!」と素直に言えていたなら、もっと早くうつから抜け出せていたのかもしれません。
感情が安定せず、家族に対してつらく当たってしまったことも、私自身を苦しめました。
家族が私をサポートしてくれると、自分が役立たずのように思われていると感じて怒ってしまったり。
うつは自分だけの病ではなく、周りをも巻き込んでしまうのだと痛感しました。
介護中のうつの症状
物事の組み立てができない(文章が考えられない、食事づくりの段取りができないなど)
介護後のうつの症状
何もやる気が起こらない(洗濯、掃除、料理などを行うことへの意欲がわかないなど)

きれいごとではなくありのままの体験を伝えたい
介護後、11年間続いたうつから抜け出したとき、介護とうつの体験を書き残そうと思いました。
介護は苦しいことも多い。介護で大変な中、私の本を手にしてくださった方には、正直にありのままの体験をお伝えして、何か一つでもヒントになればいいなと思ったのです。
泥沼があるから、蓮の花は咲ける。人も同じではないでしょうか。あの体験があったから、今、私はささやかなことにも幸せや楽しみを見出すことができるし、一食一食を大切にできるのだと思います。
介護をしていた当時の自分に、「そんなに頑張らなくていいんだよ。あなたが暗い顔していると、周りも辛くなってしまうよ」と、声をかけたいですね。
本を書いた後、当時忘れていた記憶がどんどんよみがえってきました。うつは記憶にフタをしてしまう。気分が晴れていくとともに、そのフタがとれて、点だらけだった記憶が線で結ばれていく感覚は、とても不思議でしたね。
少し“適当”なくらいがちょうどよい
今は、仕事と家族や孫のサポート、毎日の暮らしの雑用で自分の時間がほとんどない日々。
そんな生活の中での一番の楽しみは俳句づくりです。料理をしているときや孫と遊んでいるときに、パッと浮かんだ言葉を急いでスマホに入力して、後でノートに書き写すのですが、「あ、季語がなかった!」とか、見返すスタイルは面白いですね。ふと思い浮かぶのを書き留める自由さが私には合っているみたいです。
でも実は、俳句をきちんと勉強したことはありません。私はわりと大雑把な性格なので、それぐらいのほどよい“適当さ”でやるのが物事を楽しむコツなのかもしれないです(笑)。

目の前に面白いことは溢れている
この歳になっても、好奇心は旺盛な方だと思います。『鬼滅の刃』(※1)も全巻読みましたし、BTS(※2)やJO1(※3)も好き。若者のファッションもチェックしています。
先日、庭の手入れをしていたらミミズを発見しました。まだ東京にもミミズが生息できる土があるのだな、と思うとうれしくなり、しばらく見入ってしまいました。庭の木にメジロやヒヨドリが止まって鳴いている姿を見ていると、とても癒やされます。
今、世の中には自分で何かを求めなくても、テレビやネットからいろいろな情報が溢れているし、エキサイティングな場所も次々できて、娯楽がたくさんあります。でも、自分がワクワクするものは何か、選ぶのは私自身。自分の軸を持って、これからも楽しみをどんどん増やしていきたいですね。
※1 大正時代を舞台に、人と鬼が織りなす物語を描いた漫画作品
※2 韓国出身の7人組男性ヒップホップグループ
※3 日本出身の11人組アイドルグループ
安藤和津さん
あんどう・かづ●1948年生まれ。エッセイスト、コメンテーター。テレビ、ラジオなど多数の番組に出演。著書に自身の介護体験を書いた『“介護後”うつ「透明な箱」脱出までの13年間』(光文社)など。夫は俳優/映画監督の奥田瑛二。長女は映画監督の安藤桃子、次女は女優の安藤サクラ。